4. 腎臓あれこれ(コラム)
【腎臓病と高血圧】腎臓と血圧の関係をわかりやすく解説
慢性腎臓病(CKD)は、年々増加傾向にある代表的な腎臓病です。高血圧や糖尿病などの生活習慣病との関連が深く、一種の生活習慣病とも考えられています。そこで今回は、腎臓病(特にCKD)と血圧の関係をわかりやすく解説しながら、適切に血圧をコントロールして、腎臓の健康を保つための秘訣をご紹介します。
高血圧やCKDには、毎日の生活習慣が大きく関与しています。食事や運動、ストレスなど、日々の生活が体にダメージを与えている可能性もあります。まずは定期的な健康診断を受けるなど、疾病の早期発見に努めることが大切です。
参考:エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023(日本腎臓学会)https://jsn.or.jp/medic/guideline/pdf/guide/viewer.html?file=001-294.pdf
慢性腎臓病(CKD)は?わかりやすく解説します
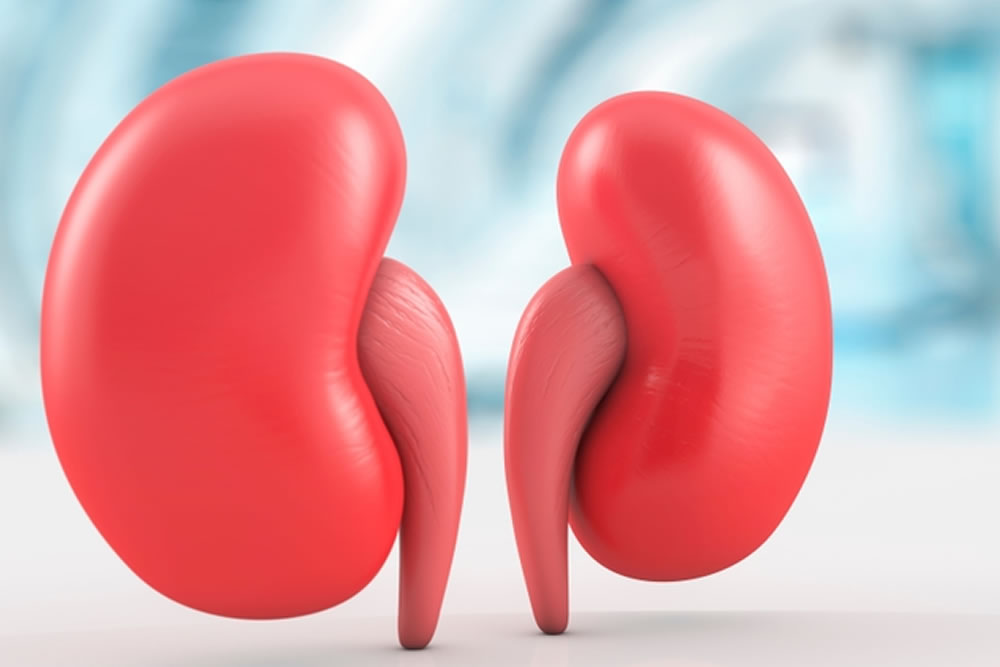
慢性腎臓病(CKD:chronic kidney disease)とは、その名前のとおり、慢性的に(ゆっくり時間をかけて経過的に)進行する腎臓の病気の総称です。尿検査や血液検査、超音波検査などで腎機能が低下しており、その状態が3ヶ月以上継続している場合に診断されます。腎臓病と血圧の関係を理解するために、まずは、CKDの基本を解説します。
CKDの定義と日本人患者数
慢性腎臓病(CKD)は、3ヶ月以上にわたり腎臓の障害(蛋白尿など)または腎機能低下(糸球体濾過量[GFR]<60 mL/min/1.73m²)が持続する状態と定義されます。慢性腎臓病(CKD)の診断には、尿検査(蛋白尿、血尿)、血液検査(血清クレアチニン、eGFR)、画像診断(腎臓超音波検査など)が用いられます。血清クレアチニン値からeGFR(推算糸球体濾過量)を算出し、腎機能を評価します。また、尿中アルブミン/クレアチニン比(ACR)や尿蛋白/クレアチニン比(PCR)を用いて、蛋白尿の程度を定量的に評価します。
日本人の慢性腎臓病(CKD)の患者さんは、約1,330万人と推計されており、成人の約8人に1人が慢性腎臓病(CKD)に該当すると考えられています。
また、慢性透析を受ける患者さんの数は、2016年末で約33万人と増加を続けており、CKDが透析導入の大きな要因となっています。このように、CKDは日本人にとって非常に身近な疾患のひとつとなっており、高血圧や糖尿病とともに、積極的な予防や治療、疾患に対する教育を行っていくことが重要と考えられています。
CKDの主な原因
そんなCKDの主な原因となるのは、糖尿病や高血圧、生活習慣病です。血糖や血圧が高い状態が持続すると、腎臓の糸球体で高血圧状態が生じ、腎臓の血流が変化し、腎実質が次第に障害を受けることで腎機能が低下します。この過程ではメサンギウムや糸球体といった腎臓の小さなフィルターの機能を果たす部分が固くなったり、大きくなったりすることがあります。
また、腎機能が多少低下したからといって、自覚症状が出ることはほとんどなく、疾患が見過ごされてしまうことも少なくありません。しかし、腎機能が低下することで、老廃物の排出がうまくいかず、体内に毒素が蓄積されやすくなり、この状態が長期間続いた結果、全身の健康に影響が及び、全身に様々な合併症が出現するようになります。
だからこそ、CKDは「早期発見と早期介入」が非常に重要であり、症状がないうちから定期的に健康診断を受けるなど、積極的な健康管理が大切です。
CKDの症状と診断方法
CKDは初期段階では自覚症状がほとんどなく、疲労感やむくみ、尿量の変化、高血圧などの症状が現れた時には病態が進行してしまっている可能性もあります。そのため、症状が出る前に腎機能低下を見つけるための、「腎機能検査」が重要となります。
腎機能の検査としては、血液検査や尿検査、画像診断(超音波やCTなど)が行われます。血液検査では、クレアチニンや尿素窒素(BUN)の値を確認し、腎機能の状態を評価します。また、尿検査では、蛋白尿の有無を確認することで、腎機能の低下を確認することができます。尿検査や血液検査など、比較的簡単な検査で腎機能の評価が可能ですので、定期的な健康診断が非常に重要となります。
そもそも高血圧とは?わかりやすく解説します

高血圧の定義と原因
高血圧は、血圧が正常範囲を超えて高くなる(高くなっている)状態を指す言葉です。成人の正常血圧は120/80mmHg未満とされていますが、高血圧は、病院で測ったときの血圧(診察室血圧)では収縮期血圧140 mmHg以上または拡張期血圧90 mmHg以上であり、家で測るときの血圧(家庭血圧)ではこれより少し低い135/85 mmHg以上で診断されます。
とはいえ、「血圧は絶対に140以下に下げなければいけない」ということではありません。年齢や基礎疾患によって血圧の目標値は異なりますので、おおよその数字として覚えておくのがおすすめです。
また、血圧には日内変動(1日の中の変化)があり、測定のタイミングや状況によっても変化することを知っておきましょう。そんな高血圧の主な原因は生活習慣です。肥満、運動不足、塩分過多の食事、ストレス、アルコールの過剰摂取など、毎日の生活によって高血圧のリスクは変化します。
※血圧には遺伝的要因もあります。
高血圧の症状と診断方法
高血圧は「サイレントキラー」とも呼ばれ、初期段階では自覚症状がほとんどありません。しかし、血圧が高い状態が長期間継続することで、心臓や血管に過剰な負担がかかり、全身にさまざまな合併症を引き起こす可能性があります。
この特徴はCKDと同様であり、「症状が出現する前に発見して予防する」ということが非常に重要になります。高血圧を早期発見するポイントは、定期的な血圧測定です。健康診断などでの血圧測定の他、家庭用血圧計を使用するなど、より頻回な血圧測定を行っておくことがおすすめです。
腎臓病と高血圧の関係

腎臓病と高血圧には非常に深い関係があります。高血圧は慢性腎臓病(CKD)の原因となり、CKDは高血圧のリスクを高めます。また、どちらも生活習慣に起因して発症するという特徴があるため、「日々の生活習慣によって血圧コントロールが乱れ、それに伴って腎機能が低下し、腎機能低下によってさらに血圧が上がりやすくなってしまう」、という悪循環が生じる可能性があります。
この悪循環を断ち切るためにも、早期発見と適切な対策が重要になります。
高血圧が腎臓に与える影響
高血圧は腎臓に直接的な負担をかけ、腎機能を低下させる要因となります。血圧が高い状態が続くことで、腎臓の細かい血管がダメージを受け、腎臓の機能が低下しやすくなります。腎機能が低下することで、体内の老廃物や水分の排泄が上手くいかなくなり、さらに血圧が上昇する原因となってしまいます。
また、腎臓は血圧を調節するホルモン(レニン)を分泌しており、腎機能が低下することで、これらのホルモンのバランスが崩れ、高血圧を引き起こす原因となります。このように、腎臓病と高血圧は相互に影響しており、「一方が一方の引き金となる」というような、悪循環を形成する可能性があります。
CKDと高血圧の治療方法
CKDと高血圧には深い関係があるため、治療においては、それぞれを単独で治療するだけではなく、双方に対してアプローチするような治療戦略を立てることが重要となります。たとえば、血圧を下げる薬(降圧薬)を使用する際には、「腎保護作用」のある薬剤を選択するなど、腎機能への影響も考慮しつつ、高血圧の治療をすすめていくことが大切です。
降圧薬の役割と種類
CKDと高血圧の治療には、降圧薬(血圧を下げる薬)が重要な役割を果たします。降圧薬には、アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬、アンジオテンシンII受容体拮抗薬(ARB)、カルシウム拮抗薬、利尿薬などがあります。
これらの薬は、血圧を下げることを主な目的としていますが、血圧を下げることで間接的に腎臓への負担を軽減することが可能になります。また、ARBやACE阻害薬といった薬剤には、直接的な腎保護作用も確認されていますので、高血圧を伴うCKDの患者さんに対しては、これらの薬剤が積極的に使用されることが多いです。
生活習慣改善の重要性
生活習慣の改善も、CKDと高血圧の治療において非常に重要です。具体的には、適切な食事、定期的な運動、ストレス管理、禁煙、適度な飲酒といった、「健康的な生活」を意識することが大切です。
特に、塩分の摂取量を適切に管理することが重要であり、医師や栄養士の指導の下、バランスの取れた食事を心掛けることが重要です。
高血圧の運動療法
CKDと高血圧の管理には、適度な運動が欠かせません。有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、サイクリングなど)は、肥満の予防だけではなく、高血圧や糖尿病といった生活習慣病への対策として重要になります。
しかし、運動療法は、体への負担もかかってしまうため、必ず医師や理学療法士などの専門家と相談しながら、無理のない範囲で体を動かしていくことが重要です。いきなりジョギングから始めるのではなく、ゆっくりとした散歩からスタートしたり、炎天下の日中を避け、早朝や夕方などの時間を選んでウォーキングするなど、過度な負担がかからないように注意しましょう。
CKDと高血圧の予防と治療
高血圧は、初期症状がほとんどなく、自覚症状が出現した時には、すでに病態が進行してしまっているというケースも少なくありません。病態を放置してしまうと、心筋梗塞や脳梗塞といった、心血管系の重大な合併症のリスクとなる他、CKDの進行によって、腎不全や透析導入のリスクが高まります。
だからこそ、自覚症状がないうちに、高血圧や腎機能低下の兆候を捉え、適切な治療を開始することが重要です。そのためには、定期的な健康診断(検診)や検査が欠かせません。
検診では、血液検査や尿検査、血圧測定などを行なうことによって、体の隠れた疾患を早期に発見することができます。自分では気がついていなかったような、血圧や腎臓の状態を知ることで、より早い段階から治療をスタートすることができます。
CKDと高血圧は相互に影響を与えており、どちらかを発症するともう片方の状態も悪化しやすくなるという悪循環が生じる可能性があります。より健康的な体を維持するためにも、定期的に健康診断を受け、必要に応じて適切な治療を行なうことが重要です。