4. 腎臓あれこれ(コラム)
慢性腎臓病(CKD)の治療方法をどこよりもわかりやすく解説
慢性腎臓病(CKD)は、腎臓の機能が徐々に低下していく進行性の疾患です。CKDは高血圧や糖尿病などの基礎疾患や生活習慣病が原因となることが多く、放置すると腎不全に進行する可能性もあり、早期発見と適切な治療が重要になります。そこで本記事では、CKDの基礎知識から症状、診断方法、治療方法、そして生活の注意点までを詳しく解説します。CKDの進行を遅らせ、生活の質(QOL)を向上させるために知っておきたいことを紹介しますので、毎日の生活習慣を見直し、腎臓のケアを心がけるようにしてみて下さい。
参考)エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2018(日本腎臓学会)
慢性腎臓病(CKD)とは?

慢性腎臓病(Chronic Kidney Disease、CKD:しーけーでぃー)は、何らかの原因によって腎臓の機能が徐々に低下し、放置すると最終的には腎不全にまで至る可能性のある進行性の疾患です。CKDは腎臓の機能が正常な状態から5つのステージ(G1/G2/G3a・G3b/G4/G5)に分類されています。ステージ1(G1)からステージ5(G5)にかけて腎機能が悪化していくイメージです。このステージ分類には、腎臓の働きを示す「推算GFR(糸球体ろ過量)」という数値が使用されるほか、尿中のタンパク質(微量アルブミン尿)の有無、血圧、その他の臨床的因子も考慮されます。そのため、CKDを正しく診断するためには、血液検査や尿検査に加え、血圧測定や病歴の確認などの包括的な評価が必要です。
CKDの原因
CKDの主な原因は、高血圧や糖尿病などの生活習慣病です。高血圧は、腎臓の血管に負担をかけることで、腎機能を低下させてしまう可能性があります。また、糖尿病を発症すると、高血糖状態によって腎臓の細かい血管がダメージを受けてしまい、腎機能が低下しやすくなります。その他の原因として、慢性糸球体腎炎、多発性嚢胞腎、薬剤性の腎障害なども挙げられますが、加齢や基礎疾患などの「生活習慣」が、CKDの発症に大きく関わっています。
CKDの症状
CKDの初期段階では症状がほとんど現れないため、腎機能の低下に気がつかないという方も少なくありません。しかし、病状が進行すると、疲労感、むくみ、尿の変化(尿の色や泡立ち)などの症状が現れ始めます。さらに進行すると、食欲不振、体重減少、吐き気、集中力の低下、皮膚のかゆみ、息切れなどの、尿毒症とよばれる症状が出現するようになり、適切な治療を行わなければ、腎不全に至ることもあります。だからこそ、症状のない初期の段階から腎機能の低下を発見し、適切な治療を開始することが重要です。早期発見と早期治療が、CKDの進行を遅らせ、生活の質を向上させる秘訣といえます。
CKDの診断方法
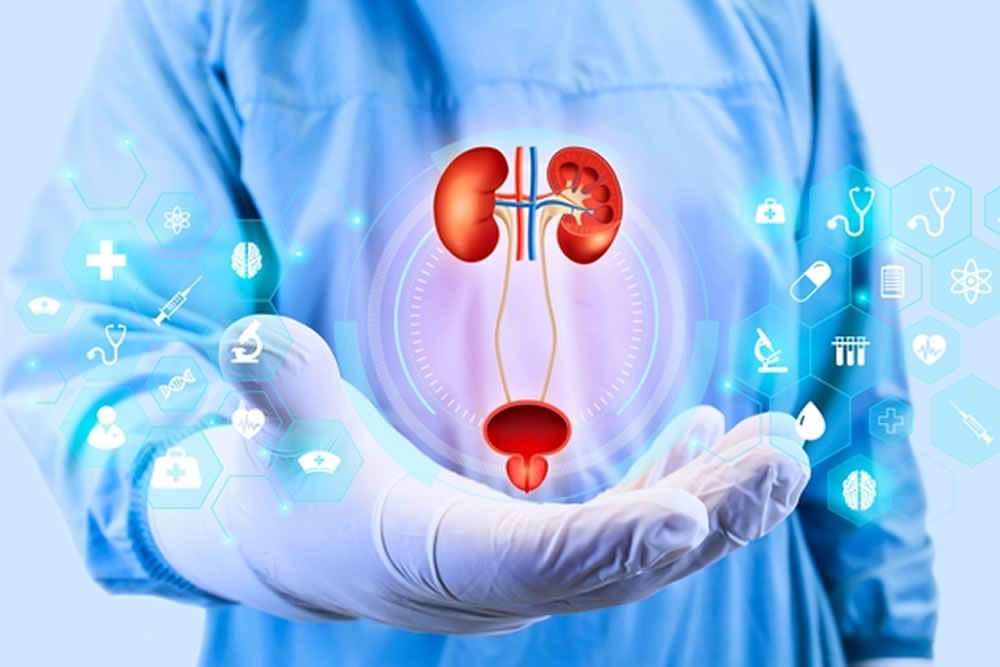
CKDは初期症状がない疾患だからこそ、定期的な検査(血液検査・尿検査)が大切です。血液検査では、「推算GFR (糸球体ろ過量)」という数値が測定され、尿検査では尿中のタンパク質の有無が確認されます。また、必要に応じて、超音波検査(エコー)やCTスキャン、MRIなどの画像診断が行われることもあります。画像検査を行うことで、腎臓自体に異常がないか(腫瘍や形状変化など)を調べることができますので、CKDと他の疾患を鑑別する上でも重要な検査となります。
CKDの治療方法
CKDの治療の基本は、生活習慣の改善と薬物治療になります。腎臓の機能を維持することはもちろん、血圧や血糖値のコントロールを適切に行うことも、CKDの進行を予防するためには重要になります。
CKD治療の目的は?
CKDの治療の主な目的は、病気の進行を遅らせることです。腎機能が低下するスピードを抑えることで、腎不全に至るリスクを減少させるだけではなく、心血管疾患(心筋梗塞や心不全など)や貧血、骨代謝異常など(骨粗鬆症など)、全身の合併症を予防することができます。また、CKD治療の重要な目標のひとつは、患者さんの生活の質(QOL)を向上させることです。腎臓の機能を維持しながら、より活力のある日常生活を送るためのサポートが、CKD治療では重要になります。症状や副作用をコントロールしながら、長く安定した治療を継続することが大切です。
血圧コントロール
CKDの治療としては、血圧管理が非常に重要です。降圧薬(ACE阻害薬やARBなど)を適切に使用することで、血圧を適切な範囲に保つことで腎機能を保護していきます。特に、ARBとよばれるタイプの薬剤には「腎保護作用」も確認されていますので、血圧をコントロールしながら腎臓の機能をサポートできる可能性があります。いずれにせよ、毎日の血圧管理はCKD治療に直結します。用法用量を守って正しく血圧の薬を使用することはもちろん、食生活や運動習慣などにも注意することが大切です。
糖尿病管理
糖尿病が原因でCKDを合併している場合、適切な血糖コントロールが必須となります。糖尿病の重大な合併症のひとつに「糖尿病性腎症」があるほど、糖尿病(血糖値)と腎機能には深い関連があります。毎日の血糖値のコントロールを適切に行うことで、糖尿病そのものの病態を改善するだけではなく、腎機能の低下を未然に防ぐことも可能になります。
その他の薬物療法
CKDの治療には、その他の薬物療法も含まれます。例えば、貧血を治療するためのエリスロポエチン製剤や、骨代謝異常を予防するためのビタミンD補充療法などが必要になる場合があります。腎臓は、血液の成分を作ったり、ビタミンDの活性化を行うなど、全身の機能に影響を与えるような様々な働きをしています。腎機能が低下することで、これらの働きが弱まり、結果的に貧血や骨粗鬆症などの合併症が出現しやすくなります。それら合併症に対する治療(予防)を行うことも、重要なCKD治療のひとつといえます。
食事療法
CKDの治療では、毎日の食生活を改善する「食事療法」が重要となります。塩分摂取の制限やタンパク質の制限、カリウムやリンなどの摂取量を管理することが大切です。また、腎機能の状態や基礎疾患(高血圧や糖尿病)の有無によって、注意すべき食事(栄養素)は異なります。必ず、医師や栄養士の指導の下で、食生活の改善に取り組むようにしましょう。
タンパク食制限の注意点
CKD治療のためには、適切にタンパク質を制限する「タンパク食制限」が効果的であると報告されています。一方、高齢者では、タンパク質の摂取制限に伴う低栄養などの問題も生じる可能性があり、一概にタンパク制限を行うことを推奨することが難しいことも事実です。だからこそ、タンパク質や塩分などの栄養素の制限を行う際には、腎臓専門医と管理栄養士を含む、医療チームの管理下で行われることが望ましいと考えられています。インターネットなどの情報だけを見て、自己判断で無理なタンパク食制限(塩分制限や水分制限も同様)をしてしまわないように注意しましょう。
運動・禁煙・ストレスの管理
適度な運動は、CKDの進行を遅らせるために有効です。ストレッチやウォーキング、ジョギング、サイクリングなどの有酸素運動を日常生活に取り入れることが大切です。とはいえ、突然強度の高い運動をすると、全身に過度な負荷がかかってしまう可能性があります。医師と相談しながら、無理のない範囲で運動を始めてみましょう。また、喫煙は腎臓に悪影響を与えるため、禁煙が強く推奨されます。さらに、ストレスは血圧や血糖値に悪影響を与えるため、適切なストレス管理を行うことも重要と考えられています。運動や禁煙、ストレスの管理など、これらライフスタイルの改善は、CKDの治療だけではなく、高血圧や糖尿病などの進行を予防することにも繋がり、全身の健康を維持するための効果的な治療戦略ともいえるでしょう。
CKD治療における禁煙の重要性は?

喫煙が悪性腫瘍の発生や心血管疾患(心筋梗塞や心不全など)発症の危険因子となることはよく知られており、CKD患者さんにおいても、喫煙が死亡率や心血管疾患発症率、CKDの進展に影響を与えることが報告されています。また、喫煙は、CKD発症の原因となるような、高血圧や糖尿病などにも大きな影響を与えるため、できるだけ早くから禁煙を開始することが大切です。必要に応じて「禁煙外来」や「禁煙治療」を利用するなど、適切な禁煙方法を選択するようにしましょう。しかし、禁煙治療を行う場合、禁煙補助薬であるバレニクリン(チャンピックス)の副作用である嘔気は、CKD患者で頻度が高いことが報告されているため、投与量には十分な注意が必要です。CKDや基礎疾患があるという方が禁煙外来を利用する際には、必ず基礎疾患の状態や服薬中の薬剤を伝えるようにしましょう。
CKDは早期発見と早期治療が重要です
慢性腎臓病(CKD)は、初期段階では自覚症状が少なく、知らず知らずのうちに進行してしまうというのが怖いところのひとつです。そのため、定期的な検診や血液検査、尿検査が早期発見には欠かせません。CKDを早期に発見し、適切な治療を開始することで、腎機能の低下を遅らせることができ、合併症の発症や腎不全に至るリスクを大きく減少させることができます。また、生活習慣の改善もCKDの治療には重要です。高血圧や糖尿病の管理、バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙といった対策がCKDの進行を防ぐための効果的な手段となります。症状がなくても定期的な検査を受けるなど、CKDの発症を未然に防止し、より健康的な生活ができるようにしましょう。