4. 腎臓あれこれ(コラム)
コーヒーが腎臓に悪影響を与えるって本当?コーヒーと腎臓病の関係を解説
今回は、コーヒーの成分とその健康効果、腎臓の基本的な役割、コーヒーが腎臓に与える影響について詳しく解説します。 また、研究結果(エビデンス)を基に、コーヒーの適切な摂取方法や腎臓の健康を守るための生活習慣についてもご紹介します。 コーヒーを楽しみながら、腎臓の健康を維持するための秘訣を解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
※2024年12月現在の情報です
コーヒーは健康にいいって本当?
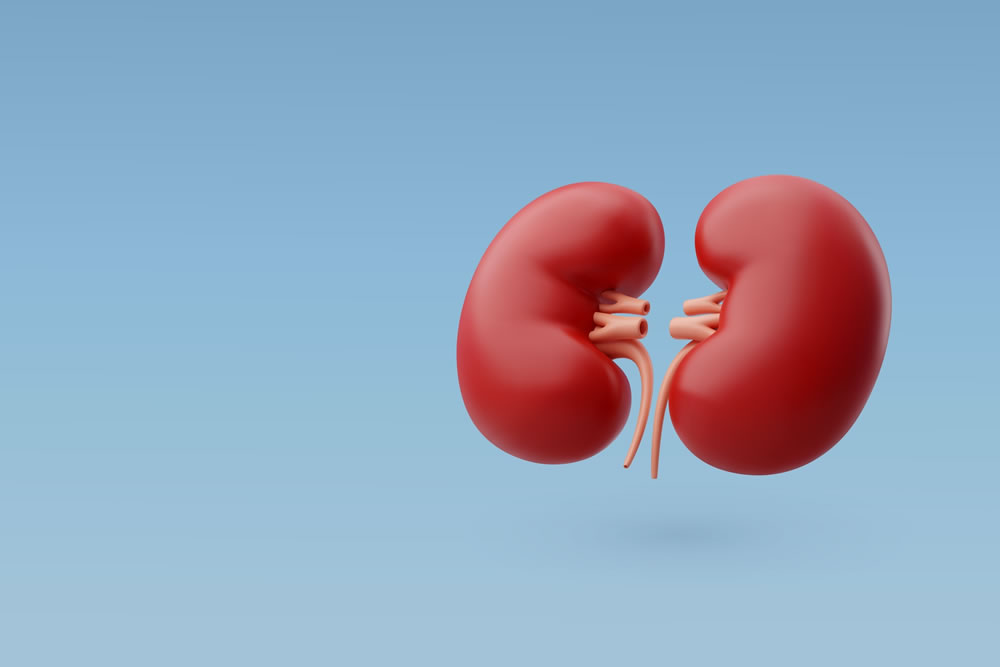
コーヒーは世界中の多くの人々に愛される飲み物であり、日本人にも馴染み深い飲料です。 だからこそ、その成分や健康効果については多くの研究が行われています。 コーヒーには、カフェイン、抗酸化物質、ビタミンB群、マグネシウムなどが含まれており、これらの成分が、さまざまな健康効果をもたらすと考えられています。
しかし、これらの成分には、メリットだけではなくデメリットがあることも理解しておく必要があります。 例えば、カフェインには覚醒作用があり、眠気を覚まして集中力を高めるような働きが期待できます。 一方、寝つきが悪くなってしまったり、動機や不安感などを誘発するなどのリスクもあります。
このように、コーヒーの成分には、魅力的な健康効果がありますが、「摂取すればするほど良い」というものではなく、心身に悪影響を及ぼす可能性があることも知っておくことが重要です。
【ポイント】コーヒーには様々な健康効果が期待できるが、飲み過ぎや基礎疾患には注意が必要。
コーヒーの成分と健康効果
コーヒーに含まれる具体的な成分や健康効果をご紹介します。 先にも簡単にご紹介しましたが、コーヒーにはカフェインという物質が豊富に含まれており、覚醒作用や集中力の向上をもたらします。 「コーヒーを飲むとスッキリする」と感じる方も多いかと思いますが、これにはカフェインが影響している可能性があります。
コーヒーのカフェインにはたくさんのメリットがありますが、飲み過ぎると「寝つきが悪くなってしまう」という方も少なくありません。 そのため、カフェインが苦手という方や、夜寝る前にもコーヒーを飲みたいという方は、「カフェインレスコーヒー(デ・カフェ)」を試してみることもおすすめです。
コーヒーにはポリフェノールという抗酸化物質が含まれており、抗酸化物質には細胞の老化を防ぐ効果がありますので、カフェインレスコーヒーであっても、抗酸化作用を期待することができます。
コーヒーを飲むおすすめのタイミングは?
コーヒーの飲み方は人それぞれですが、一般的には朝食時や仕事の合間に飲むことが多いのではないでしょうか。 ブラックコーヒーとして飲む人もいれば、ミルクや砂糖を加えて飲む人もいます。
コーヒーの健康効果を引き出すためには、適切な摂取量とタイミングを意識することが大切です。 肥満や血糖値などへの影響を避けるためには、砂糖やミルクなどの使用を最小限にすることがポイントです。
ミルクを使用する際にも、低脂肪ミルクや無脂肪ミルクを選択すると、脂質や糖質を抑えることができます。 また、睡眠が浅くなったり、睡眠の質が低下することを防ぐためにも、できる限り寝る前のコーヒーは避けることがおすすめです。
腎臓の基本的な役割

腎臓は、血液中の老廃物をろ過し、尿として排出する働きを持つ重要な臓器です。 背中側の腰の上辺りに左右ひとつずつ存在しており、握りこぶし大ほどの大きさをしています。
腎臓は、体内の水分や電解質のバランスを維持し、血圧の調整やホルモンの生成にも関与していますので、腎臓の機能が低下すると、全身に様々な影響が出現する可能性があります。
腎臓の機能
腎臓は1日に約200リットルの血液をろ過し、必要な栄養素を再吸収し、不要な物質を尿として体外に排出する役割を担っています。 再吸収とは、必要な栄養素を再び体内に取り込み、より効率的に体を維持するための機能です。
また、腎臓はエリスロポエチンというホルモンを生成することで、赤血球の生成に関与しています。 そのため、腎機能に障害が出現すると、赤血球の生成が低下し、結果的に貧血のような症状が出現するようになります。 これを腎性貧血とよびます。
このように、腎臓には、「血液のろ過」以外にも様々な働きがあり、全身の機能維持に重要な役割をしています。
腎臓の健康を保つためには?
腎臓の健康を保つためには、適切な食生活、水分補給、定期的な運動、ストレス管理が重要です。
特に、バランスの取れた食事を心掛けることが、腎臓の健康維持には非常に重要であり、塩分や水分の摂取量によっては、腎臓に負担がかかってしまう可能性があります。
現時点での研究では、適量(1日2〜3杯)のコーヒー摂取が腎機能に悪影響を与えるという具体的なエビデンスは不足しています。 ただし、過剰摂取は他の健康問題を引き起こす可能性があるため注意が必要です。
※2024年現在の情報
コーヒーが腎臓に与える影響
ここからは、コーヒーが腎臓(腎機能)に与える影響について詳しく解説します。 コーヒーが腎臓に与える影響については、多くの研究が行われていますので、代表的な研究結果も合わせてご紹介します。
コーヒーと腎臓のエビデンス
コーヒーの摂取が腎機能や健康に及ぼす影響については、世界中で様々な研究が実施されています。
- コーヒーの摂取と死亡リスク
- コーヒーの摂取と腎臓病のリスクの関係性
- カフェイン摂取とCKDの関係
コーヒーの摂取と死亡リスク
こちらの研究では、様々な人種を対象に、「コーヒーの摂取が全体的な死亡リスクおよび特定の原因による死亡リスクにどのように影響するか」が調査されています。
研究結果として、コーヒーの摂取が全体的な死亡リスクを低減し、特に心血管疾患や消化器系疾患による死亡リスクを低下させることが示されました。 1日2−3杯のコーヒーが死亡リスクを減少させる可能性が示唆されたことで、コーヒーの健康効果について、より多くの注目が集まるようになりました。
参考:Association of Coffee Consumption With Total and Cause-Specific Mortality Among Nonwhite Populations
コーヒーの摂取と腎臓病のリスクの関係性
この研究では、様々な人種を対象に、「コーヒーの摂取が全体的な死亡リスクおよび特定の原因による死亡リスクにどのように影響するか」が調査されています。
研究に参加した45歳から64歳の14209名の参加者を追跡調査(中央値24年)したところ、コーヒーの摂取が全体的な死亡リスクや発症リスクを低減することを示しました。 特に心血管疾患や消化器系疾患による死亡リスクを低下することや腎臓病の発症リスクが低下することが示されました。
カフェイン摂取とCKDの関係
この研究では、慢性腎臓病(CKD)患者を対象にカフェインの摂取が死亡リスクに与える影響を調査しました。
結果は、カフェインの摂取がCKD患者の全体的な死亡リスクに悪影響を及ぼさないということが示されました。 逆に、CKD患者のカフェイン摂取と全死亡率の間に逆相関関係があることが検出されています。
参考:Caffeine consumption and mortality in chronic kidney disease: a nationally representative analysis
コーヒーの適切な摂取方法

上記のような様々な研究が行われており、コーヒーの摂取が「むしろ腎機能に良い影響を与える可能性がある」ということが示唆されています。
とはいえ、コーヒーの摂取量や摂取タイミングには注意が必要であり、多くの研究では、「1日2〜3杯」のコーヒーが推奨されています。
この範囲内であれば、コーヒーの健康効果を発揮しつつ、コーヒーやカフェインによるデメリットを減少させることができる可能性があります。
コーヒーを飲むタイミングと頻度
基本的に、コーヒーは朝食時(朝食後)や昼食後に飲むことがおすすめです。 夕方以降の摂取は、睡眠に影響を与える可能性があるため注意が必要です。
また、空腹時に飲むと胃を刺激することがあるため、空腹時の摂取は避け、食事とともに摂取することで血糖値や血圧への影響を最小限に抑えられます。
また、ブラックコーヒーが苦手という方の場合、ミルクや砂糖の量には十分な注意が必要です。 甘いミルクコーヒーは、糖尿病や肥満を助長する可能性も考えられます。
コーヒーの摂取は医師にご相談ください

今回は、コーヒーの摂取と腎臓の関係について紹介しました。
2024年現在の見解では、おおむね、「適度なコーヒーは健康に良い影響を与える」と考えられています。
とはいえ、基礎疾患や体質などによっては、コーヒーによって体調を崩してしまうかもしれません。
だからこそ、医師や栄養士などの専門家と相談の上、コーヒーを含めた食生活の見直しを行なうことがおすすめです。
腎臓の健康を維持するためには、毎日の食生活が非常に重要です。
バランスの取れた食事、適度な運動、十分な水分補給、ストレス管理を心掛け、定期的な健康診断を受けることで、腎臓の機能を保つことができます。
腎機能をより長く維持するためにも、定期的な健康診断を受け、定期受診を心がけるようにしましょう。