4. 腎臓あれこれ(コラム)
腎臓の7つの働きや機能をわかりやすく簡単に解説します!
腎臓の働きとしては、「血液をろ過して尿中に老廃物を排出する」というものが有名です。しかし、腎臓の働きはこれだけではなく、実際には、全身の機能に非常に重要な役割を担っています。そこで今回は、腎臓が有する7つの機能をわかりやすく解説し、腎臓の健康が全身にどれほど影響を与えているかをわかりやすく解説します。また、腎臓病の予防と管理のために気をつけるべきポイントもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧下さい。
腎臓の重要性と基本的な役割
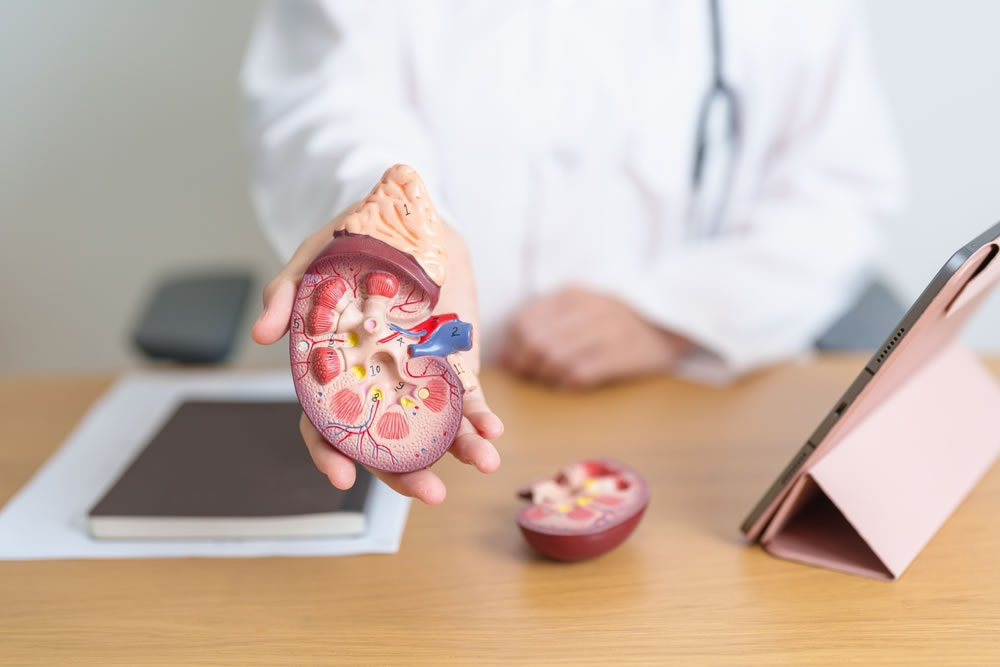
腎臓は、人体で「浄化装置」としての役割を担う重要な器官(臓器)です。浄化装置とはあくまでもイメージなのですが、血液中から老廃物や毒素、余分な水分などを濾過して、それを尿として排出するような働きをしています。そのため、腎臓の機能が低下してしまうと、体内の水分バランスが乱れて浮腫(むくみ)などが出現したり、体の中に毒素や老廃物がたまりやすくなってしまいます。全身を巡る血液を浄化させるような、非常に重要な役割を持っているのが腎臓です。
腎臓の位置と構造をわかりやすく
腎臓の位置は腹部の背中側(腰の上あたり)にあり、左右に一対(左右ひとつずつ)存在しています。一般的には、大人の握り拳ほどの大きさで、そら豆のような形をしています。左右一対の腎臓があるため、何らかの理由でどちらかひとつの腎臓しかないような状態を「片腎」と表現することがあります。さらに、腎臓の構造をより詳しくみていくと、腎臓には、毛細血管がかたまりになったものが糸球体とそれに続く尿細管をネフロンと呼ばれるものが存在します。また1つの腎臓には100万個のネフロンが存在します。
糸球体とは?
糸球体は、細い毛細血管が毛糸の球のように丸まった構造をしている部分です。糸球体は0.1ミリ~0.2ミリほどの大きさであり、1つの腎臓に約100万個の糸球体があるといわれています。
尿細管とは?
尿細管は、腎臓の糸球体からホースのように続く、曲がりくねった管です。この管(尿細管)の中を原尿(尿のもと)が通過していく過程で、糸球体でろ過された尿が徐々に再吸収されていきます。糸球体でろ過しすぎてしまった、体の中で必要な成分(アミノ酸やミネラルなど)を再び体の中に戻す働きが「再吸収」です。糸球体から尿細管を通して、ろ過と再吸収を効率的に行なっていくようなシステムが構築されています。
ネフロンとは?
1つの糸球体とそれに続く尿細管をひとまとめにした構造のことをネフロンと呼びます。1つの腎臓に約100万個の糸球体があるということは、そのそれぞれがネフロンの構造を作っており、各腎臓には100万個のネフロンが存在することになります。
腎臓の構造や機能を把握するためには、糸球体・尿細管・ネフロンといった、それぞれの部分の働きを理解しておくことが大切です。
参考: 一般社団法人 日本腎臓病学会. https://jsn.or.jp/general/ ,(参照2024-06-25)
腎臓の主な機能とは?
腎臓の主な機能は、体内の余分な水分や老廃物を血液中からろ過し、尿として体外に排出することです。この働きは、上記で紹介したネフロンによって行われます。これにより、腎臓は体内の水分バランスを維持し、必要な電解質やミネラルを調整し、血液のpHを正常に保つ役割を果たしています。体の中の水分のバランスを調整しているようなイメージをもっておくと、腎臓の機能が理解しやすくなります。また、腎臓は、血液をろ過するだけではなく、血圧の調整や赤血球の産生を促進するホルモンの生成、骨の形成に関わるビタミンの活性化など、全身の機能維持に非常に重要な役割をしています。「腎臓は尿を作る場所」というのは間違いではありませんが、実際の腎臓の機能はそれだけではなく、全身を支える様々な働きをしています。
腎臓と膀胱の違い

腎臓と膀胱は共に尿路系の重要な器官であり、しばしばその働きが混同されています。たしかに、腎臓と膀胱は、尿の生成や排泄に非常に重要な働きをしていますが、その役割と機能には大きな違いがあります。各臓器の機能や働きの違いを紹介します。
腎臓の役割
腎臓は、血液をろ過することで、体内の老廃物や余分な水分を尿として排出する役割を担っています。血液ろ過の過程で、腎臓は、体内の水分バランスや電解質の調整、酸塩基平衡の維持、さらには血圧調節や赤血球生成など、非常に様々な生理機能をコントロールしています。そのため、腎臓の機能が低下すると、泌尿器系のみならず、全身の様々な臓器や働きに大きな影響が出現する可能性があります。
膀胱の役割
腎臓と混同されやすい器官が「膀胱」です。膀胱は、腎臓から送られてくる尿を一時的に貯蔵するための袋状の臓器です。膀胱は、尿をためておく「貯蔵タンク」のような役割を持っており、適切なタイミングで尿を体外に排出するような働きをしています。膀胱の壁には筋肉があり、これがギュッと収縮することで、尿を勢いよく体外に排出することができます。そのため、膀胱の機能に異常が生じると、尿をためておけなくなってしまったり、尿のキレがわるくなってしまったり、頻尿になるなど、排尿全般に影響が出る可能性があります。
知っておきたい腎臓の7つの働き

腎臓は非常に多くの生理機能を担っており、全身への影響が非常に大きい重要な臓器のひとつです。知っておきたい、腎臓の7つの主要な機能について詳しく解説します。
1. 体内の老廃物の除去
腎臓の基本的な機能は、血液中の余分な水分や老廃物をろ過し、尿として排出することです。生命活動を維持するためには、必要なエネルギーや栄養素を体の中に蓄えながら、老廃物や毒素、不要な水分などを効率的に体外に排泄する必要があります。腎臓が行っている「血液のろ過」は、「必要なものは残して、いらないものは捨てる」といった、非常に高度なシステムなのです。
2. 余分な水分の排出調節
腎臓は体内の水分バランスを調節する働きがあります。水分が過剰または不足している場合、腎臓は水分の再吸収量を調整し、体の水分レベルを適切に保ちます。腎臓の機能が低下することで、体内に老廃物がたまりやすくなるだけではなく、水分を効率的に排出できなくなり、結果的にむくみが生じる可能性があります。そのため、腎機能が低下している方の場合、水分摂取量を厳密に守る必要があり、水分摂取や塩分摂取に制限が設けられることがあります。※腎機能のレベルによって制限は異なります。
3. 電解質バランスの維持
ナトリウム、カリウム、カルシウムなどの電解質は、体内の様々な生理反応に必要不可欠な物質です。腎臓は、これらの電解質の濃度が適正な範囲で保たれるように調整する働きをしています。電解質バランスが乱れると、むくみやめまいなどの症状が出現する他、心拍や血圧、神経伝達や筋肉の収縮、心臓の機能などにも影響する可能性があります。
4. 酸塩基平衡(ph)の維持
腎臓は、体内のpHレベルを一定に保つ役割も担っています。血液のpHバランス(酸性やアルカリ性などのバランス)を正常な範囲内で保つことができるのも、腎臓の働きによると考えられます。
5. 血圧調節
腎臓は「レニン」という酵素を分泌することで、全身の血圧を調節する働きをしています。レニンの作用によって、血圧に関与する「アンジオテンシンⅡ」というホルモンを作り出すことができ、これらの物質が血圧を至適範囲内でコントロールしてくれています。腎臓の機能が低下すると、レニンが上手く分泌できなくなってしまい、血圧を調節する能力は低下するため高血圧になる傾向があります。
6. 赤血球産生の促進
腎臓は、エリスロポエチン(EPO)というホルモンを生成することで、赤血球の生成を促進する働きをしています。エリスロポエチンは骨髄にて赤血球の産生に関わっているため、エリスロポエチンの低下は、赤血球産生の低下を意味します。そのため、腎機能が低下することで、エリスロポエチンの生成が抑制され、結果的に赤血球が減少し、その結果、貧血症状が生じます。この症状を「腎性貧血」とよびます。
7. 骨の健康維持(ビタミンDの活性化)
腎臓は、ビタミンDを活性化する役割も担っています。ビタミンDの活性化は、カルシウムやリンの代謝に関与しており、骨の健康に大きく影響します。腎臓の機能が低下すると、ビタミンDが活性されなくなり、丈夫な骨を維持できなくなり、骨折や骨粗鬆症のリスクが高まります。
腎臓の健康を保つための日常生活の注意点

上記でご紹介したように、腎臓には様々な働きがあり、それが全身の機能に影響しています。だからこそ、腎臓の健康を保つことは非常に重要であり、そのために欠かせないのが「規則正しい生活習慣」です。適切な食生活、定期的な運動、禁煙などの生活習慣は、腎臓の健康に直結します。
食生活
適切な食生活は腎臓の健康を保つ上で非常に重要です。たとえば、塩分の摂取量を意識することで、血圧をコントロールし、腎臓への負担を減らすようにしましょう。また、水分の不足や過剰摂取にも注意が必要です。一人ひとりの腎機能やライフスタイルによっても必要な水分量は異なりますが、適切な水分摂取を意識することが大切です。
運動習慣
定期的な運動は、全身の血流を改善し、高血圧や糖尿病といった腎臓病のリスク因子にも良い影響があります。また、運動は体重管理にも役立ち、肥満の予防につながります。とはいえ、急に運動をすることで、体に大きな負荷がかかってしまう可能性もあります。運動習慣を取り入れる際には、運動の強度などをかかりつけ医に相談するようにしましょう。
生活習慣の改善
生活習慣の改善は、腎臓病予防には必要不可欠です。健康的な食生活を心がけ、定期的な運動を行い、禁煙することが、腎臓病だけでなく、他の多くの疾患から健康を守る秘訣となります。毎日の生活習慣を見直してみましょう。